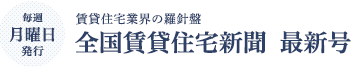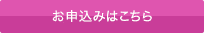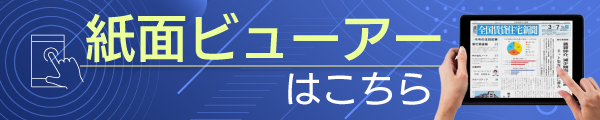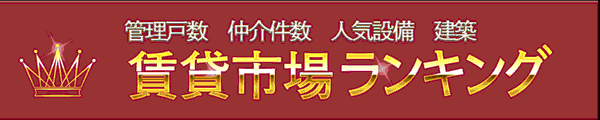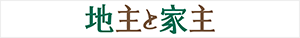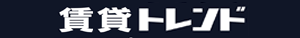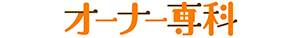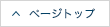新型コロナウイルス下で、企業のテレワーク導入により住まいの立地が職場で縛られなくなりつつある。在宅時間が増えた中、物件選びの要素に街そのものの魅力が意識され始めている。街の魅力を入居者に発信し、地域での入居者コミュニティーの醸成に重きを置く管理会社・オーナーの事例を紹介する。
モノづくりの講師役で地域住民と交流
巻組、移住者が街に溶け込む 子どもや高齢者と接点
空き家を改修したシェアハウスの運営を行う巻組(宮城県石巻市)は、石巻市に全5棟19室のシェアハウスを運営し、「田舎ならではの生活を楽しみたい」と希望する県外からの移住者が入居者の9割を占める。現代アート、洋裁、木工、木彫などといったアート・モノづくりを行う入居者が多いことから、制作物の物々交換を行うイベントやワークショップを同社で企画し地域住民との交流の機会を提供している。
コロナ下で多様化した働き方の選択肢により、入居者の属性にも変化があった。東京と地方の両方にフィールドを持ちたい人の増加。リモートワークが可能になったことで地方ならではの漁業や狩猟などの一次産業に従事しながら、別の時間でパソコンでの事務仕事を行う事例もみられるという。
そんな入居者の中には、会社員兼モノづくりを行うクリエイティブな人も多く、入居者主催で地域住民向けの占いやものづくりイベント、作品展示を行うこともある。
2020年は月に1回同社主催の「物々交換市」を開催。地域に住む高齢者から子どもまでが参加し、入居者の制作物との交換や、入居者が講師となる木彫・アートペイントのワークショップを提供しこの体験とモノを物々交換する。
拠点は地域にある倉庫をリノベーションしたアトリエ兼・コワーキング。ワークショップでは地域の子どもだちが喜んで参加している様子が見られたという。
渡邊享子社長は「地域に関わる受け皿として機能していきたい。コロナ下で柔軟に変化した働き方のおかげで、山や海に囲まれた地方に来て地域の仕事を体験したいという声も増えている。漁業などの人手不足の分野に手伝いを希望する入居者もいる。人口減少地域の持続化に努めていきたい」と語る。
巻組
宮城県石巻市
渡邊享子社長(33)
グローバルエージェンツ、地元のみこし担ぐ 仲間とともに参加
全国に49棟2987戸のコミュニティー型賃貸「ソーシャルアパートメント」を運営するグローバルエージェンツ(東京都渋谷区)では、「WAVES日本橋浜町」(東京都中央区)で入居者が街のコミュニティーに参加するきっかけづくりを行っている。地域イベントの開催情報の告知を行うことで一部の入居者が街のコミュニティーに参加し、街の活性化に寄与している。
19年3月にオープンした同物件は都営新宿線「浜町」駅から徒歩6分に立地する。14階建ての全54部屋。入居者の年齢層は20代後半~30代前半。21年8月時点での入居率は90%だ。
オーナーや町内から共有される地域イベントの情報を、同社が入居者への直接の声掛けや入居者間のオンライン掲示板ツールで情報を発信している。
コロナ下以前には、対面でのイベントが盛んに行われていた。コミュニティーマネジメントを行う事業者が主催する、浜町エリアの住人とエリアのオフィスに勤める人を対象にした月1回の交流会。また、2年に1回5月に開催する神田祭、7月の納涼祭、8月の盆踊りについてこれまで入居者へ情報を共有してきた。
特に19年の神田祭では、2日間の開催で計22人の入居者が参加。このうち12人は「WAVES」という物件名を印刷した法被を制作し、みこしを担いだという。
入居者が参加した神田祭の様子
同物件の営業担当者である菊地麗子氏は「街のイベントに興味はあっても、個人で参加の仕方を調べることはハードルが高い。物件単位で地域コミュニティーイベントの情報を共有することで参加しやすくなる効果はあると思う」と語る。
今後は、コロナ下において入居者の働き方が変化したことで街への関わり方にも変化が生まれると同社では考える。出社のため地域イベントが開催される時間に参加できなかった入居者が、テレワークにより昼間も街へ出かけられる機会が生まれることを期待する。
シェアスペース設置 コミュニティー拠点目指す
オーナーが自ら仕掛け人になって、入居者と地域との橋渡しになっているケースがある。神奈川県内に5棟37戸を所有し、自主管理を行う木村憲司オーナーだ。地域に価値を還元してくれる人や、地域コミュニティーのある生活を送りたい人を入居者として自身の物件に迎え入れ、所有物件を満室稼働させている。
20年10月末ごろからは、ファミリー向けに貸し出していた1階にテナントの入る3階戸建て賃貸住宅の2~3階部分を入居者の退去後にシェアスペースとして開放。利用対象は木村オーナーの物件に住むすべての入居者と二子新地エリアに住む地域住民だ。
利用料は、入居者は管理費の中に含むとし実質無料、ボランティア活動など売り上げが立たない利用用途の場合は無料としている。
木村オーナーは「利用料を取らないのは、この場所を拠点にさまざまな特技を持つ人が交わってほしいから。シェアスペースが、利用者同士のコミュニティーを生み地域へ還元できる事業などが生まれる場として機能すれば、この場所が所有物件全体の価値を上げると考える」と話す。
シェアスペースとして開放した当初から、平日の月~金曜日に一部スペースで花屋が店舗を構えている。曜日ごとに店番が変わり、入居者や地域住民であるフォトグラファーの学生や油絵などを手がけるイラストレーター、ミュージシャンなどが店に立つ。
21年5月に所有物件の共有スペースで開催したイベント。地域住民と入居者7組が運営を担う
木村オーナーの物件の入居者であり花屋の代表を務める白川崇さんは「さまざまな業種の人が花屋をやることで、そのスタッフの友人知人が店に出向いてくれ、街を訪れるきっかけとなる。また、異色な花屋として口コミが広がることを狙い、多くの人が立ち寄るコミュニティーの拠点となりたい」と話す。
木村オーナーは「地域住民から、『木村さんの物件に住む入居者はよくあいさつをしてくれる』と報告されたことがある。自分が行ってきた地域と入居者をつなぐきっかけづくりの効果を実感した」と語る。
地域活動に参加するという感覚から、入居者自身が地域活性のための活動の運営を担うようになってくれることを理想とし、今後も入居者と地域住民の接点を提供していきたいとする。
木村憲司オーナー(50)
神奈川県川崎市
(8月23・30日4面に掲載)
おすすめ記事▶『用途転換で収支改善!築古建物再生 ~前編~』