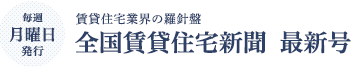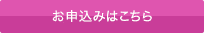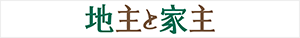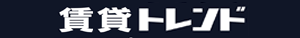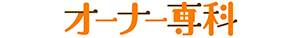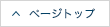空き家の利活用において、行政と民間企業はどのように連携すれば良いのか。「賃貸住宅フェア2024in大阪」では、大阪市生野区の筋原章博区長と、空き家活用(東京都港区)の和田貴充社長が、官民連携の理想的な始め方を語る。
業務委託の体制を打破
背景は外国人増加
生野区と空き家活用は、空き家情報の掘り起こしで連携している。2023年より実証実験を開始し、24年から生野区のホームページに空き家専門の相談窓口「アキカツカウンター」を設置。空き家所有者から寄せられた相談には、空き家活用のスタッフが対応する。
生野区が空き家の情報収集に乗り出した背景には、外国人の増加がある。人口12万人超に対し、すでに5人に1人が外国人であるにもかかわらず、これらの人々が働ける機会や場所が少ないという課題があった。一方で、増え続けるシャッター商店街や空き家を活用できないかと考えた。
区は、2023年5月より複合施設「いくのパーク」を開業。多文化共生の拠点として、外国人を対象とした飲食業のスタートアップ支援セミナーを実施する。外国人向けの仕事を創出しつつ、同セミナーの受講生が飲食店を開業する際に空き家を活用してもらう狙いがある。空き家活用とは、同支援プログラムにおける空き家実態調査とデータベースの構築、空き家活用啓発イベントの実施でも連携する。
"異和共生"の考え方
筋原区長が大切にしている考え方がある。「異和共生」といって、立場や考え方の違いを認め合い大切に思い合って、一緒にできることを少しずつ広げていくというものだ。この考え方で、官民連携を推進してきた。
生野区長への就任以前も、大阪市大正区、港区と市内の区長を歴任してきた筋原氏。大正区と港区では、空き家リノベーションの成功事例を作り、リノベ済みの築古ビルなどを拠点に定期マーケットイベントを開催して、にぎわいを創出するというまちづくりを仕掛けてきた立役者だ。生野区でのまちづくりは、二つの区でのノウハウを集結させた、集大成だと語る。
民間が先陣切る
筋原区長は「業務委託にとどまってしまう官民連携では、街にインパクトを与えることができない」と話す。行政も民間もお互いに頼り過ぎず、同じ目的に向かって互いにできる一歩を踏み出していく連携の形を理想とする。これが、異和共生の考え方に通ずる点だ。
一方で和田社長は、民間企業側の姿勢で必要なことを次のように語る。まずは行政からの補助金支給を前提とせず、民間企業がプロジェクトをスタートさせる。そのうえで、行政にサポートを依頼する。サポートを受けるために意識したいポイントとして、民間企業の独り善がりな事業ではなく、国策に当てはまっているかという視点を持つことも重視するべきだという。
互いに受け身同士ではない官民の連携が実現したとき、空き家再生によって街の不動産価値を上げられるかもしれない。
空き家活用
東京都港区
和田 貴充 社長(48)
大阪市生野区
筋原 章博 区長(61)
<筋原章博氏のキャリア>
2010年に大阪市大正区の区長に就任。その後17年より同市港区の区長に、22年より現職。「異和共生」を基本理念に、複合施設「Tugboat Taisho(タグボート大正)」(ミスべリング・イノベーター大賞)、シェアアトリエ「ヨリドコ大正メイキン」(都市住宅学会会長賞)などのプロジェクトを公民地域連携で実施。エリアの価値向上に取り組む。
(2024年12月2日20面に掲載)