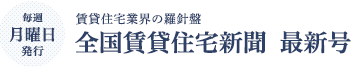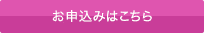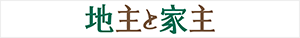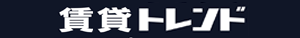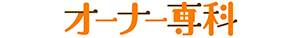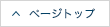【2024年10大ニュース】編集部が選ぶ2024年ニュースランキング
エステムプランニング,ジェイエーアメニティーハウス,アットホーム,LIFULL,リクルート,経済産業省,APAMAN,Good(グッド)不動産,明和不動産,公益財団法人日本賃貸住宅管理協会,健美家,ファーストロジック,帝国データバンク,日本銀行,アンビションDXホールディングス,みんなで大家さん販売,都市綜研インベストファンド,全国賃貸住宅修繕共済協同組合,東急不動産,日鉄興和不動産
物価上昇の影響、各所に
2024年、賃貸業界で注目度の高かったニュースをランキング形式で紹介する。業界で最も実感を伴う話題として受け止められているのは、家賃改定の活発化だろう。物価高騰を背景に、東京、名古屋、大阪の三大都市圏を中心として、家賃が上昇している事例が多く見られた。そのほかにも、印象深いニュースを振り返る。
災害や高齢化対策、重要度増す
1.家賃改定が活発化
第1位は、活発化する家賃改定だ。建築費や人件費などの高騰の影響から、特に三大都市圏では一次取得者層向けの住宅価格が高騰。賃貸にとどまるファミリー層が増え、賃貸の需要が高まる傾向も見られた。一方で物価上昇に伴い賃貸住宅の運営コストも増加。これらの状況から、管理会社による賃貸住宅の家賃値上げの動きが活発化した。
家賃上昇についてはエリアによって濃淡があったようだ。1月20日〜2月5日を調査期間とした、管理物件における家賃の値上げ状況を調べた全国賃貸住宅新聞独自調査では、半数以上で「値上げを実施した」という結果が出た。家賃の値上げ幅は1000〜3000円未満の回答が63.6%と最多となった。家賃の改定を実施した理由については、「管理物件の運営コストが上がったから」が32.5%を占めた。また、「近隣物件の家賃相場が上昇しているから」という旨の回答が31.2%となった。
値上げを実施した企業の本社所在地は「東京都」がトップで32.2%。次いで、「東京都を除く関東」が27.3%、「九州・沖縄」が14.3%と続いた。
管理戸数1万4000戸超のエステムプランニング(大阪市)は築5年以上の物件に1年以上入居している5020世帯に対し、一斉に家賃値上げの通知書を送付。家賃アップに合意したのは71.2%になったと当社の取材に回答している。物価上昇も続いていることから、家賃アップの流れは25年も続くのではないかと予想される。
2.能登半島地震
第2位は、1月1日に発生した能登半島地震だ。一部破損を含む住宅への被害は約14万棟となった。賃貸住宅も被災し、漏水や設備の故障が多発。被災エリアの管理会社は、被害状況の確認や対応に追われた。
被災者の住宅確保が急務となった。国土交通省は被災者に対し、県外の公営住宅の空き住戸を提供。石川県は、県内の公営住宅のほか、民間の賃貸住宅を活用した賃貸型応急住宅(以下、みなし仮設)などを提供して支援を図った。みなし仮設とは賃貸住宅の空室を国や自治体が借り上げて、被災者へ一時的に提供する住宅のこと。県内の不動産3団体を窓口に、入居希望者へ住宅をあっせんした。地場や大手の不動産会社も支援に動いた。被災者への空室の提供や家賃・仲介手数料を減額するなど、独自の支援策を次々に発表した。
震災時に重要な役割を果たしたみなし仮設だが、一方で今後の課題も浮かび上がった。ファミリー向け物件の空室が少ないことや、被災者のメンタルケアといった入居後の支援体制の不足が挙げられる。
能登半島地震後、管理会社が行う被災者支援の重要性がより増していると考え、みなし仮設に関する研修を実施する管理会社もあった。ジェイエーアメニティーハウス(神奈川県平塚市)は、6月に営業担当者向け研修を実施。災害時に備え、研修を今後も実施する予定だという。
管理物件の被災状況(写真はいずれもクラスコ提供)
3.省エネ性能表示制度、開始
第3位は、「省エネルギー性能表示制度」の開始だ。4月1日以降に建築確認を申請した賃貸住宅においては、入居募集時に所定の「省エネ性能ラベル」を表示することがオーナーやサブリース会社の努力義務となった。主に新築建築物の広告が対象だ。
さらに、11月からは、既存住宅において部位ごとに省エネ性を可視化する「省エネ部位ラベル」制度も開始。新築に加え、既存住宅の省エネ表示化も努力義務とされ、賃貸業界では対応を急ぐ。
制度開始に伴い、ポータルサイト運営各社は、性能ラベルや部位ラベルが表示できるよう準備を進めた。「SUUMO(スーモ)」「LIFULL HOME,S(ライフルホームズ)」「不動産情報サイトアットホーム」の3サイトは、両ラベル共に画像を入稿すると物件の詳細ページ上に表示されるように変更している。25年は、情報の正確性を担保しつつ、各社がいかに運用するかを注視したい。
省エネ性能ラベル(上)と省エネ部位ラベルの画像イメージ
4.LPガス、法規制で料金透明化
第4位は、液化石油(LP)ガスの料金の透明化だ。経済産業省資源エネルギー庁は4月、「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令」を公布した。2段階に分けて改正省令を施行し、取り締まりを強化する。
背景には、LPガス事業者と賃貸オーナーの間の商習慣と依存関係がある。具体的には、LPガスの契約を締結する代わりに、エアコンなどの設備を「無償貸与」するというもの。LPガス事業者が無償貸与した設備費は、入居者が負担するガス料金に上乗せする商習慣が問題視されてきた。この慣行が、不透明なガス料金体系の温床となり、入居者がLPガス事業者を自由に選べない状況を生み出していた。
1段階目として経産省は、LPガス事業者に対し「過大な営業行為」を禁止する改正省令を7月に施行。エアコンの無償貸与など、正常な商習慣を超えた利益供与を禁止する。LPガス事業者の切り替えを制限するような条件付き契約の締結も禁止し、違反者には罰則規定も設ける。罰則対象はLPガス事業者。ただし、設備の無償貸与を求めるオーナーや、オーナーへの過大な営業行為をあっせんする不動産会社も、事実上違法行為のほう助に等しいとみなされる可能性がある。
2段階目として、25年4月からは、三部料金制を徹底する省令を施行する。LPガス事業者は、利用者に通知するガス料金の明細の中で、基本料金、使用料を表す従量料金、設備料金の3項目に分けて利用料金を提示することが義務化される。
不動産会社やオーナーは、直接的な罰則対象ではないものの、LPガス事業者へ設備貸与を強要していないか、経産省は国交省と定期的な情報共有を実施している。