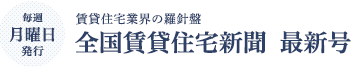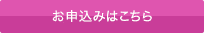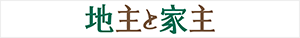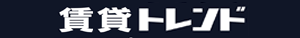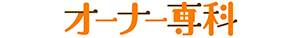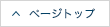【資格一覧】賃貸業界で役立つ!不動産資格20選【2025年最新版】
その他|2025年04月03日
不動産賃貸業界で生かせる資格にはどのようなものがあるか。
不動産賃貸業界の現場では、不動産管理・仲介に係る法務や、リフォーム・リノベーション、相続支援など、幅広い知識が求められる。だが、OJT(職場内訓練)で膨大な不動産知識をすべて身に付けることは難しい。社員教育の一環として資格取得を支援する会社も増えてきた。不動産に関する資格の勉強をすることで、実務に生かせる幅広い知識を体系的に習得できる。資格を持っていることで、オーナーや入居者からの信頼の獲得にもつながる。
本記事では、不動産賃貸業界の現場で活用できる資格を、活用シーン・目的別に紹介する。
INDEX
▶王道の国家資格
①宅地建物取引士
②賃貸不動産経営管理士
▶修繕・リフォーム・原状回復を学ぶ
③賃貸住宅メンテナンス主任者
④敷金診断士
▶空室の入居付けに使える
⑤ホームステージャー
⑥福祉住環境コーディネーター
▶相続提案で差別化
⑦相続診断士
⑧相続支援コンサルタント
⑨相続アドバイザー
⑩家族信託コーディネーター
▶中古物件に強くなる
⑪ホームインスペクター(住宅診断士)
⑫古民家鑑定士
▶投資家の心をつかむ
⑬ファイナンシャル・プランニング(FP)技能士
⑭投資不動産取引士
⑮投資不動産販売員
⑯不動産実務検定
⑰公認 不動産コンサルティングマスター
▶不動産のスペシャリストになる
⑱不動産鑑定士
⑲CPM(IREM認定不動産経営管理士)
⑳CCIM(CCIM認定不動産投資顧問)
↓ 以下の表をクリックすると、詳しい一覧をご覧いただけます ↓
![]()
王道の国家資格
不動産業に関わる国家資格の中から、賃貸住宅業界で特に必要とされる国家資格を二つ紹介する。
一つ目は基本中の基本、宅地建物取引士(宅建士)。宅建士には独占業務がある。不動産取引における「重要事項説明(重説)」「重要事項説明書への記名」「契約書への記名」は宅建士でないと行うことができない。
二つ目は、2021年の賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(賃貸管理業法)施行に伴い、国家資格となった賃貸不動産経営管理士(賃貸管理士)だ。
宅地建物取引士
●資格保有者数:56万8353人(宅建士証交付者、2023年度末時点)
●合格率:18.6%(2024年度)
●試験方法:択一式
●試験日(2024年):10月20日
●検定料:8200円 (非課税)
●実施機関:一般財団法人不動産適正取引推進機構
宅建士は、不動産業界では必須の資格だ。宅地建物取引業法(宅建業法)において、営業所の業務従事者の5人に1人は、専任の宅建士を配置しなければならないと定められている。宅建士は、不動産取引にまつわる法律などの体系的な知識を求められる。
宅建士には独占業務があり、賃貸、売買どちらにおいても、不動産取引を行う際に必要不可欠な業務だ。宅建士資格が必要な業務として、以下の三つが挙げられる。
〇重要事項説明
〇重要事項説明書(いわゆる35条書面)への記名
〇契約書(いわゆる37条書面)への記名
オンライン会議システム「Zoom(ズーム)」などを活用したIT重要事項説明(IT重説)や電子契約でも、もちろん宅建士は必要不可欠となる。
宅建士の資格保有者に資格手当を出している企業も多い。
また、宅建士は不動産業界全般で通用する。賃貸管理業のみならず売買仲介や不動産投資など、幅広い分野で役立つだろう。
試験内容は宅建業法、権利関係、法令上の制限、税・その他の4科目に分けられ、細かい法令知識や最新の統計情報も出題される。不動産に関する実務経験が長くても、全く勉強しないで受かる試験とはいえない。2024年度の合格率は18.6%だ。
それぞれの分野について対策を十分に講じて試験に臨むべきだろう。
試験対策に役立つ!【連載】全賃新聞の宅建試験丸わかり解説はこちら↓
「宅建試験解説」に関するニュース一覧 :: 全国賃貸住宅新聞
賃貸不動産経営管理士
●資格保有者数:7万7598人(登録者数、23年4月時点)
●合格率:24.1%(24年度)
●試験方法:択一式
●試験日(24年):11月17日
●検定料:1万2000円(非課税)
●実施機関:一般社団法人賃貸不動産経営管理士協議会
賃貸管理士は、賃貸住宅管理業を行ううえで設置が義務づけられている「業務管理者」の要件の一つとされる資格で、2021年に国家資格化された。賃貸不動産の専門家として、賃貸住宅の管理業に関わる幅広い知識、倫理観、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(管理業法)の知識を有することが求められる。
2021年に施行された管理業法において、200戸以上の賃貸管理を行う企業は、各事業所・営業所へ業務管理者を1人以上配置することが義務づけられた。これから業務管理者を目指す場合は賃貸管理士試験に合格し、一定の実務経験を経るか、所定の講習を修了する必要がある。
ただし、業務管理者になることのみを目的とするならば、賃貸管理士試験を受験しない「宅建士ルート」もある。宅建士に登録している場合、一定の実務経験を持ち講習を受講することで業務管理者の要件を満たすことが可能だ。とはいえ、賃貸管理士試験の勉強で学ぶ内容は、賃貸業界で働く人にとって必須の知識ばかり。特に賃貸仲介・管理事業やサブリース事業を行う企業に勤めている場合は役立つ場面が多いだろう。賃貸管理士の資格保有者に対し、資格手当を出す会社もある。宅建士ルートが可能な人でも、賃貸管理士試験を受ける価値は十分にあるだろう。
試験内容は、管理業法から管理実務、関連法令・制度、相続、税務、経営など。試験50問のうち5問を免除できる指定の講習もある。
賃貸管理士試験の合格率は、2021〜2023年の3年間は30%前後で推移していた。2024年度は3万3949人が申し込み、受験者は3万194人、合格者数は7282人、合格率は24.1%だった。
試験対策に役立つ!管理士試験対策の解説はこちら↓
「管理士試験対策」に関するニュース一覧 :: 全国賃貸住宅新聞
修繕・リフォーム・原状回復を学ぶ
賃貸不動産の管理や入居者の退去時にはさまざまなトラブルが想定される。トラブルの未然防止・解決のためには、建築・設備の知識はもちろん、原状回復に関する法令知識など幅広い知識が求められる。ここからは、賃貸管理の現場で必要となる修繕やリフォーム、原状回復に関する知識を習得できる資格を二つ紹介する。
賃貸住宅メンテナンス主任者
●資格保有者数:1万8921人(2024年6月11日時点)
●合格率:ー
●試験方法:択一式
●試験日:随時
●検定料:9900円(税込み、テキスト・講習動画など含む)
●実施機関:公益財団法人日本賃貸住宅管理協会
賃貸住宅メンテナンス主任者(メンテナンス主任者)は、23年11月に創設された民間資格だ。低層アパートや戸建てを中心とした賃貸住宅の設備、維持保全における基礎知識を体系的に学べる。
24年6月11日時点で試験への申込者数は2万1319人、資格保有者は1万8921人に上る。
メンテナンス主任者の取得を推進する管理会社は増えている。
狙いの一つ目は、一次対応の質の向上だ。建物メンテナンスの実質的な作業は、施工会社や設備工事事業者が行うことが多い。だが、顧客の問い合わせに直接対応するのは管理会社だ。管理会社での一次対応が明確でない場合、顧客からの不信感につながる。例えば水漏れ一つをとっても、水漏れした箇所によって止水栓を閉める指示が必要なほか、深刻な水漏れの場合は、水道の元栓を閉める指示を顧客に出さなければならない。メンテナンス主任者の資格があれば、そうした一次対応の質が向上する。
狙いの二つ目は、建物修繕・維持の提案精度の向上だ。資格取得により、修繕事業者の言うことを鵜呑みにせず、工事価格が適正なのか、工事を今すべきか、繰り延べするべきかといった判断の精度向上につなげることが期待できる。
メンテナンス主任者はオンライン試験でいつでも受験できる。試験を受験する前に、オリジナルの公式テキストと講習動画で学習する。テキストはデジタル版もあり、講習動画はスマートフォンでも視聴できるため、隙間時間を活用して勉強できる。
創設されてまだ間もないが、今後も引き続き注目度は高まっていくことが見込まれる。特にオーナーへの修繕提案、原状回復に携わる賃貸管理業の従業員にお勧めできる資格だ。
実際に資格取得を推進する3社に取材をした記事はこちら↓
一次対応や修繕提案を強化【クローズアップ】 :: 全国賃貸住宅新聞
(公財)日本賃貸住宅管理業協会会長へのインタビュー記事はこちら↓
メンテナンス主任者資格は実務に生きる? 日管協塩見会長に 設立の背景を聞く :: 全国賃貸住宅新聞
敷金診断士
●資格保有者数:624人(登録者数、2024年7月17日時点)
●合格率:ー
●試験方法:択一式
●試験日:随時
●検定料:7800円(非課税)
●実施機関:特定非営利活動法人日本住宅性能検査協会
敷金診断士は、不動産賃貸における敷金・保証金を巡るトラブルの解決を図る専門家として、特定非営利活動法人日本住宅性能検査協会(東京都中央区)が認定する民間資格だ。
退去立ち会い業務には多くの知識と経験が求められる。設備の知識に乏しければ、例えばキッチンの排水管の水漏れなどを見逃してしまい、次の入居後すぐにトラブルになってしまうことがある。契約者が退去精算の負担割合に納得できず、費用面でもトラブルとなり次の入居に支障が出てしまう可能性もあるだろう。
敷金診断士では、こうしたトラブルの防止・解決を図るため、敷金や原状回復に関わる法令知識と建築知識を学ぶことができる。
敷金診断士は、法務大臣認証ADR機関である一般社団法人日本不動産仲裁機構(同)の実施する、ADRの「調停人」の基礎資格の認定を受けている。ADRとは、裁判外紛争解決制度と訳され、裁判手続きによらずに紛争を解決する手段のことをいう。合格後に一定の条件を満たせば、調停人として登録することができる。調停人は、通常は非弁業務として禁止されている調停など当事者同士のトラブル解決に向けて、合法的に仲裁に入る。
調停人が活躍する場面の例を次に挙げる。「賃借人の退去時、原状回復費用を大幅に超える多額の請求を賃貸人からされてしまった」「部屋に多数の破損があったが、原状回復に見合う費用を払ってもらえなかった」「明確な判断基準がないにもかかわらず、賃貸人から敷金が返還されない」など。どのケースも賃貸の現場で起こり得る案件だ。敷金診断士の次に、調停人として登録すれば、活躍の幅は広がるだろう。
調停人に登録するためには、敷金診断士に合格した後、調停人候補者研修の受講が必要だ。研修費用は6万500円で、年間登録料は1万800円(いずれも税込み)。
空室の入居付けに使える
賃貸管理・仲介の現場で、何としても解決したい「空室」。実際、空室対策に奔走する営業担当者は多いことだろう。そこで、入居付けに使える知識・技能の資格を二つ紹介する。
ホームステージャー
●資格保有者数:5000人以上(2024年8月21日時点)
●合格率:【2級】85%程度(2022年)
●試験方法:講座受講、実技、択一式、記述式
●試験日:随時
●検定料:
【1級】(HOME(ホーム)・LIFE(ライフ))11万円
【2級】(来場型・オンライン型)3万3000円、(eラーニング型)2万9700円
(いずれも税込み)
※一般社団法人日本ホームステージング協会加入の場合、料金が異なる
●実施機関:一般社団法人日本ホームステージング協会
「ホームステージング」とは、空室に家具などを配置することで、入居を決めやすくする手法のことだ。内見者が暮らしをイメージしやすくなり、物件も魅力的に見えるようになる。
各種物件ポータルサイトへの掲載画像に、ホームステージングをしている室内画像を掲載している不動産会社も多い。
ホームステージャーは、2013年に創設された一般社団法人日本ホームステージング協会(東京都江東区)が認定する民間資格。ホームステージングの技法だけでなく、整理収納、インテリアなどの知識を体系的に学ぶことができる資格だ。同協会の杉之原冨士子代表理事は、「ホームステージングという新しいスキル・知識を身に付けることが差別化につながる」と資格取得の意義を語る。
受講者の職業別内訳を見ると、不動産仲介業・不動産管理業が47.7%と約半数を占める。
1級・2級と難易度別に2種類あり、1級は2級保有者のみに受験資格がある。
2級の試験内容は、セミナー受講とその後の試験で、選択式25問。80点以上で合格となる。試験内容はホームステージング概論、片付け・遺品整理など。
1級は、ホームステージングの技法だけでなく、居室の撮影方法などもセミナーで学ぶ。選択式の試験のほか、小論文や実技試験もある。
「ホームステージング白書2022」の調査では、ホームステージングを実施した物件の71%が、それまで入居付けが困難な物件・長期空室物件であったにもかかわらず、ホームステージングの実施後1カ月以内に成約に至ったという調査結果が出ている。
空室対策に向けて、ホームステージャー資格の取得を目指してみてはいかがだろうか。
日本ホームステージング協会代表理事への取材記事はこちら↓
日本ホームステージング協会、ホームステージング広める :: 全国賃貸住宅新聞
福祉住環境コーディネーター
●資格保有者数:ー
●合格率:【1級】14.5%(2023年度第51回)、【2級】41.8%(2024年度第52回)【3級】40.8%(2024年度第52回)
●試験方法:択一式
●試験日(2024年):
【1級】12月15日
【2・3級】7月12日~8月1日、11月15 日~12月5日
●検定料:
【1級】9900円【2級】7700円【3級】5500円(いずれも税込み)
●実施機関:東京商工会議所
東京商工会議所(東京都千代田区)が認定する福祉住環境コーディネーターは、医療・福祉・建築について体系的な知識を学べる民間資格だ。
「超高齢社会に対応できる賃貸住宅とは何か」を専門的知見からオーナーにアドバイスできる。リフォーム時に、バリアフリー改修の知識を活用することが可能だ。
賃貸仲介・管理の現場ではなじみの薄い資格ではあるが、オーナーに対し物件の差別化につながる提案ができるだろう。
1級・2級・3級と難易度別に3種類の検定がある。合格率は2、3級のほうが1級と比べて高いため、比較的取得しやすいといえる。
相続提案で差別化
管理会社にとってオーナーの相続は、ビジネス上で重要なターニングポイントだ。超高齢社会の中、管理会社が代替わりに立ち会う機会はますます増えている。相続をきっかけに管理替えされてしまうことは少なくない。
オーナーとの関係性を2代、3代にわたって構築するため、士業と連携して相続セミナーを開催するなど、相続支援に積極的に取り組む管理会社も増えてきた。次世代オーナーの信頼を得られれば、さらなる管理受託につなげられる。
オーナーから「安心して相談できる」と感じてもらえるよう、相続に関する資格の取得を目指してみてはいかがだろうか。
関連コンテンツ:
【ダイジェスト】相続支援研究会の管理会社に聞いた! 相続支援業務の現状 | 賃貸トレンド
相続診断士
●資格保有者数:ー
●合格率:ー
●試験方法:択一式
●試験日:随時
●検定料:
【個人受験】(初回)3万8500円【再受験】1万6500円【団体受験】3万3000円
(いずれも税込み)
●実施機関:一般社団法人相続診断協会
一般社団法人相続診断協会(東京都中央区)が認定する民間資格。相続診断士は相続に関する基礎知識を身に付けたうえで、顧客の「相続診断」を行う。同法人によると、相続診断とは、相続手続きに関する問題点の指摘や、相続に関する情報提供を行うことをいう。
試験内容は、相続に係る税制やその関連法、実務に関する知識など。選択式60問で問われる。不動産分野以外の内容も含まれるため、幅広く体系的に学習する必要がある。
関連記事
ホワイトホームズ、自社オフィスで相続セミナー :: 全国賃貸住宅新聞
相続支援コンサルタント
●資格保有者数:3169人(2024年4月1日時点)
●合格率:ー
●試験方法:
【一般】講習受講、択一式試験
【上級】講習受講、記述式試験、プレゼンテーション
●試験日(24年):
【一般】11月21日
【上級】11月28日・29日
●検定料:
【一般】(通常)17万6000円、(賃貸管理士取得者)11万円、(会員)8万8000円
【上級】(通常)22万円、(会員)11万円
(いずれも税込み、講習受講料含む)
●実施機関:公益財団法人日本賃貸住宅管理協会
公益財団法人日本賃貸住宅管理協会(以下、日管協:東京都千代田区)が認定する、相続コンサルティングの資格だ。
相続税や遺言といった不動産相続に関する基礎知識が身に付く「相続支援コンサルタント」と、セミナー講師などに必要な説明力が身に付く「上級相続支援コンサルタント」に分けられる。
相続支援コンサルタントの資格取得企業は1050社、取得人数は3169人(2024年4月1日時点)。日管協の田口俊輔課長は「創設当初は管理会社が相続支援を行うイメージがなく、関心を示す企業は一部に限られた。2019年ごろから大手管理会社も相続に関わるケースが増え、受講者数が増加している」と話す。
相続支援コンサルタントのセミナーで学ぶ項目は、相続を巡る社会状況から、相続税・贈与税などの賃貸不動産に関わる税制、不動産登記や民事信託まで多岐にわたる。
特に上級相談支援コンサルタントの取得は、オーナーへの相続コンサルティングやオーナー向けの相続セミナーで講師を務める人にお勧めだ。上級相談支援コンサルタントの場合、グループ形式でプレゼン発表や事例研究を行うなど実践的な講習も含まれる。資格取得を通じて相続に関する説明力を養えるだろう。
家族信託コーディネーター
●資格保有者数:ー
●合格率:ー
●試験方法:講座受講
●試験日:随時
●検定料:講習によって異なる
●実施機関:特定非営利活動法人相続アドバイザー協議会
同協議会によれば、相続アドバイザーとは、円満な相続を実現するために、実務的な視点からオーナーと各士業の間に入り、的確なアドバイスを行う専門家のことをいう。名称が似ているが、銀行業務検定である「相続アドバイザー2級・3級」とは運営団体も内容も異なる。
相続アドバイザーは、2000年の資格創設以降、「相続の専門家」として活躍する人材を育成してきた特定非営利活動法人相続アドバイザー協議会(東京都渋谷区)が認定する資格だ。
オンラインまたは対面による18講座を修了することで認定される。相続実務に詳しい司法書士や税理士など専門家による講座で、2024年は9〜12月に行われた。2025年は5〜7月の開催を予定する。
相続支援では専門家とチームを組むことも多く、ネットワークづくりが重要となる。そのため、専門家とのつながり形成を目的とした受講者もいるという。
2024年9〜12月開催の講座受講料は、初めて受講する場合は16万5000円で、再受講の場合は5万5000円(いずれも税込み)。
家族信託コーディネーター
●資格保有者数:ー
●合格率:ー
●試験方法:研修受講
●試験日:毎月1~2回程度開催
●研修料:11万円(税込み)
●実施機関:一般社団法人家族信託普及協会
家族信託とは家族間の資産運用を委託者・受託者・受益者と分割しておくことで、資産が凍結されないようにする仕組みのことだ。信託の委託者、受託者、受益者が家族で組成される点が特徴。家族信託を組成しておくことで、本人(委託者)が認知症などになったときでも賃貸収入を適切に活用したり、空室に新たに入居者を入れたり、資産の運用や処分を行うことができる。
家族信託コーディネーターは、一般社団法人家族信託普及協会(東京都千代田区)が認定する民間資格。オーナーと士業の間に入り、家族信託を活用したほうが良いかなど、ほかの選択肢と比較検討し、家族信託に関して的確な説明を行うための資格だ。
同協会に加入し、2日間の研修を受講すると認定される。
中古物件に強くなる
築古の中古物件については、構造・設備の劣化状況などの把握や、築古であることを生かす施策が重要となる。中古物件に関する専門的な知識があれば、オーナーと入居者双方の安心感につながる。
築年数が経過した中古物件を管理する際に活用できる、二つの資格を紹介する。
ホームインスペクター(住宅診断士)
●資格保有者数:ー
●合格率:29.0%(2024年9月)
●試験方法:択一式
●試験日(2024年):3月、6月、9月、12月の1~14日のうち選択指定
●検定料:1万5000円(税込み)
●実施機関:特定非営利活動法人日本ホームインスペクターズ協会
特定非営利活動法人日本ホームインスペクターズ協会(北海道札幌市)が認定する、ホームインスペクションに関わる民間資格。受験資格は問わないため、建築関連の資格がない不動産会社の従業員でも受験できる。
ホームインスペクション(住宅診断)とは、住宅の劣化や設備の寿命のほか、構造に問題はないか、改修すべき点はないかなどを確認する業務のこと。所有する不動産を売り出す前にホームインスペクションを行うことで、建物の状態を正確に把握でき、取引成立後の争いを防ぐことができる。
特に売買仲介の現場で活用できる資格ではあるが、賃貸管理・仲介の現場でも役に立つ。中古物件の設備や構造の欠陥を特定することができれば、修繕コストの管理や賃借人とのトラブル回避に生かせる。賃貸管理に携わる担当者が住宅診断について学ぶことは、長期的な建物管理の観点からも有意義だろう。
試験科目は建築、調査・診断、不動産取引・流通、倫理の四つ。パソコンを利用した試験(CBT)方式による50問の選択式で、総合得点が合格点以上、かつ部門別得点が基準点以上で合格となる。(部門別の基準点は年ごとに設定される)
古民家鑑定士
●資格保有者数:ー
●合格率:ー
●試験方法:択一式
●試験日:随時
●検定料:9000円(税込み)
●実施機関:一般社団法人住まい教育推進協会
不動産賃貸業界では取得者数の少ないであろう古民家鑑定士。築50年以上の古民家の文化的価値、希少性などについての鑑定を行う。ほかにも、古民家の新たな価値を発見し、移築や再活用などの提案を行う際に使える知識を学ぶことができる。
近年の空き家問題や地方創生の観点から、古民家の活用に焦点が当てられている。歴史的価値を踏まえた賃料設定やリノベ提案ができれば、他社との差別化につながる。古民家が多い地域の管理会社の従業員にとっては、特に有意義な資格となるだろう。
受験資格は20歳以上であれば誰でも受験可能。試験科目は総論、伝統構法、在来工法の3科目。選択式60問50分の試験だ。
投資家の心をつかむ
不動産投資家と直接関わる担当者には、投資家の立場に立って幅広く提案する力が求められる。不動産投資家が抱える長期的な資産形成の課題は多岐にわたる。適切なアドバイスができれば、顧客からの信頼獲得につながるだろう。
ファイナンシャル・プランニング(FP)技能士
●資格保有者数:ー
●合格率:
【特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会(日本FP協会)】
1級:(実技)82.4%(2024年9月)
2級:(学科)47.1%(実技)56.5%(2024年9月)
3級:(学科)86.2%(実技)85.8%(2024年4月~9月)※CBT試験
【一般社団法人金融財政事情研究会(金財)】
1級:(学科)15.95%(2024年9月)(実技)88.21%(2024年9月)
2級:(学科)19.00%(実技)40.45%(2024年9月)
3級:(学科)47.63%(実技)53.23%(2024年4月~9月)※CBT試験
●試験日(2024年):
【1級】
日本FP協会:(実技)9月8日
金財:(学科)1月28日、5月26日、9月8日
(実技)2月上旬~中旬、6月上旬~中旬、9月下旬
【2級】日本FP協会・金財:(学科・実技)1月28日、5月26日、9月8日
【3級】随時※CBT試験
●検定料:
【日本FP協会】
1級:(実技)2万円
2級:(学科)5700円(実技)6000円
3級:(学科)4000円(実技)4000円
【金財】
1級:(学科)8900円(実技)2万8000円
2級:(学科)5700円(実技)6000円
3級:(学科)4000円(実技)4000円
(いずれも非課税)
●実施機関:特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会(日本FP協会)、一般社団法人金融財政事情研究会(金財)
金融業界でよく知られる検定の一つである、FP技能検定。試験分野は、ライフプランニングと資金計画、金融資産運用、タックスプランニング、リスク管理、不動産、相続・事業承継の六つに分かれている。
職業能力開発促進法により認定された検定で、特定非営利法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会(日本FP協会:東京都港区)と、一般社団法人金融財政事情研究会(金財:東京都新宿区)の2団体で試験を実施している。
日本FP協会と金財で実施する試験は、内容が一部異なる。
2級・3級の学科試験は、両団体とも内容が同じだ。実技試験の試験科目が異なり、日本FP協会の実技試験科目は1〜3級ですべて資産設計提案業務のみ。金財の実技試験科目は3級で個人資産相談業務・保険顧客資産相談業務の2科目、2級では個人資産相談業務・中小事業主資産相談業務・生保顧客資産相談業務・損保顧客資産相談業務の4科目があり、受験者が選ぶことができる。
1級試験に関しては、学科試験は金財のみで実施され、合格率は24年9月で15.95%と狭き門だ。学科・実技いずれも受験できる2・3級と異なり、1級の場合は、学科試験に合格すれば実技試験を受けられる。実技試験は日本FP協会は筆記、金財は面接。実技試験の合格率は日本FP協会が82.4%(2024年9月)、金財が88.21%(2024年9月)といずれも高い水準だ。
活用できる業界の幅が広く、資格区分も難易度別に1〜3級と広いため取得者数も多い。もちろん賃貸住宅業界でも資格保有者は有利だといえる。オーナーや投資家の資産運用相談の際に知識を活用でき、相談会などの場面でも資格保有者ということで顧客から安心感を持ってもらいやすい。
投資不動産取引士
●資格保有者数:ー
●合格率:ー
●試験方法:択一式
●試験日(24年):4月16~21日、7月16~21日、10月15~20日のうち1日
●検定料:2万4200円(税込み、公式テキスト代など含む)
●実施機関:一般社団法人投資不動産流通協会
一般社団法人投資不動産流通協会(東京都中央区)が認定する民間資格。投資用物件の売買の基礎知識を学べる。
実需向け居住用不動産の契約書類のフォーマットを、投資用不動産用の契約書に流用している実務担当者もいるのではないだろうか。投資用不動産の場合、物件の所有者と購入者以外に賃借人である第三者が存在するため、物件の調査以外に賃貸借契約や賃料収入等の詳細を確認する必要があるなど、実需向け不動産とは違いがあるので注意が必要だ。投資不動産取引士の資格取得に向けて投資用不動産に特化した売買の実務を勉強することで、自信を持って取引の実務にあたることができるだろう。
また投資不動産取引士は、投資不動産に関するトラブルの分野において、「調停人」候補者の基礎資格として認定されている。ADRの調停人は、通常は非弁業務として禁止されている調停など当事者同士のトラブル解決に向けて、合法的に仲裁に入ることができる。資格取得後、調停人研修を受講することで、調停人候補者となれる。投資用不動産の売買市場が成長するとともに、売買によるトラブルも増加している。調停人として合法的に仲裁もできるようになれば、活躍できる幅が広がるだろう。
資格対策としては、公式テキストと試験対策講習動画を活用する。40問からなる択一式のオンライン試験を受講し、合格後は登録講習を受ける必要がある。最後に登録手続きをもって、晴れて投資不動産取引士の資格取得となる。
投資不動産販売員
●資格保有者数:ー
●合格率:46.35%
●試験方法:択一式
●試験日:随時
●検定料:7000円(税込み)
●実施機関:一般社団法人新しい都市環境を考える会
投資用マンションの販売会社を中心に構成された業界団体、一般社団法人新しい都市環境を考える会(以下、都環会:東京都新宿区)が23年に創設した民間資格。
投資用マンションの販売営業に特化した資格として、試験問題は不動産、金融、税制、社会情勢、投資リテラシーといった幅広いジャンルから構成される。
一部の不動産会社による悪質な投資勧誘が、投資用不動産業界全体のイメージダウンにつながっているという声もある。資格創設の狙いについて、都環会の北田理会長は「資格保有の有無が、健全な販売営業かどうかを判断する際の指標になることを目指す」と話す。
2023年4月〜2024年3月は、受験資格を都環会の会員企業に限定していたが、2024年4月から一般受験を開始した。9月末時点での累計受験者数は1426人だ。
試験はCBT方式で実施し、四肢択一式の40問。
不動産実務検定
●資格保有者数:ー
●合格率:ー
●試験方法:択一式
●試験日:随時
●検定料:
【1級】8800円【2級】7700円【マスター】220,880円(いずれも税込み、マスターは講座受講料・テキスト代含む)
●実施機関:一般財団法人日本不動産コミュニティー
主に不動産投資家向けに実施される不動産実務検定。
検定は2級、1級、マスターと、難易度別に3段階。検定を実施する一般財団法人日本不動産コミュニティー(東京都中央区)によれば、
〇2級は主に賃貸管理運営に関する知識・技能
〇1級は不動産投資および土地活用に関する知識・技能
〇マスターは不動産運用設計に関する専門的かつ実務的な知識・技能
を学ぶことができるとしている。
1級と2級の資格の取得方法は、講座を受講して試験を受ける方法と、試験のみを受験する方法の2パターンがある。マスターは1級と2級いずれも合格・入会したうえで、指定の講座を受講し、実技試験に合格する必要がある。
公認 不動産コンサルティングマスター
●資格保有者数:約1万5300人(2024年3月時点)
●合格率:45.2%(2023年)
●試験方法:択一式、記述式
●試験日(2024年):11月10日
●検定料:3万1500円(税込み)
●実施機関:公益財団法人不動産流通推進センター
不動産コンサルティングマスターは、不動産投資、コンサルティング業務において一定水準以上の知識があると認められることで得られる資格だ。一般的な不動産の売買、賃貸の相談だけでなく、資産の有効活用、金融、投資に関する業務の知識を深めることができる。
受験資格は厳しく、以下3種類のうちいずれかの国家資格保有者に限られる。
①宅地建物取引士
②不動産鑑定士
③1級建築士
さらに、資格登録要件もあり、①〜③それぞれの業務で5年以上の実務経験がなければ、試験に合格しても登録することができない。ただし、実務経験が3年以上5年未満の場合は、不動産流通推進センターが指定する講習を修了すれば登録できる。
不動産のスペシャリストになる
ここからは、不動産分野のスペシャリストを目指す人にお薦めの資格を紹介する。試験に合格するための勉強時間が多く必要で、ほかの資格と比べて費用が高い資格もあり、相当な覚悟を要する。だが、不動産賃貸業界に勤める人も、今後不動産業界で専門家として活躍するための資格として一考の余地はある。
不動産鑑定士
●資格保有者数:8695人(2024年1月時点)
●合格率:【短答式】36.2%【論文式】17.4%(2024年)
●試験方法:択一式、論述式
●試験日(2024年):
【短答式】5月19日【論文式】8月3~5日
●検定料:
電子申請:1万2800円(非課税)
書面申請:1万3000円(非課税)
●実施機関:国土交通省
弁護士・公認会計士と並ぶ三大国家資格の一つ、不動産鑑定士。
不動産鑑定士は、法規制や地理条件などを踏まえて不動産鑑定評価書を作成することができるようになる資格だ。自治体からの委託を受けて、地価公示価格などの根拠となる公的鑑定業務などを担う。不動産の鑑定業務は、不動産鑑定士の独占業務となっている。不動産鑑定士以外が不動産の鑑定を行った場合、刑事罰の対象となる。
試験は短答式、論文式の2回。短答式試験の合格者は翌年と翌々年の2年間、短答式試験が免除され論文式に挑むことができるため、試験勉強を年で分けることができる点はメリットといえる。
2024年における短答式の受験者は1675人で合格者は606人、論文式の受験者は847人で合格者は147人だった。
CPM(IREM認定不動産経営管理士)
●資格保有者数:7800人(うち国内706人)(2024年3月)
●合格率:ー
●試験方法:セミナー受講、択一式、記述式
●試験日(2024年):会場により異なる
●検定料:【会員】79万9000円【非会員】96万円(税込み、公式セミナー受講料含む)
●実施機関:一般社団法人IREM JAPAN(アイレムジャパン)
CPMは、IREM(アメリカ・シカゴ)が認定する資格。不動産の管理・運営、投資分析などに深い知識・高い専門性を持つと認められた人に付与される。
CPMの取得要件として、まず不動産管理業務経験と管理戸数が一定以上であるほか、試験に合格するために金融や不動産管理、リーシングなどに関する公式セミナーも受講する必要がある。
試験は2段階。CPM検定試験に合格後、最終試験がある。CPM検定試験はセミナーで学んだ内容を中心に出題される。最終試験は、与えられた物件情報・管理情報などを基に管理改善提案レポートを作成する。最終試験は択一式と記述式で、100問5時間の長丁場だ。
CCIM(CCIM認定不動産投資顧問)
●資格保有者数:ー
●合格率:ー
●試験方法:ポートフォリオ提出、セミナー受講、試験
●試験日:随時
●検定料:195ドル
●実施機関:一般社団法人CCIM JAPAN(ジャパン)
CCIMは、THE CCIM INSTITUTE(シーシーインスティテュート、全米認定不動産投資顧問協会:アメリカ・シカゴ)が認定する事業用不動産に関する資格。
公式セミナーを受講することで、事業用不動産に関する財務・市場の分析方法などを学び、論理的な投資判断を行う力を身に付けられるとする。2024年度の公式セミナーは一括申し込みの場合、会員で77万円、非会員で84万7千円。公式セミナーですべての科目を修了し、ポートフォリオの提出と最終試験の合格を経て、アメリカのTHE CCIM INSTITUTEへ本部会費を支払えば称号を取得できる。
ポートフォリオが承認される要件は、過去5年以内に事業用不動産の取引実績が一定数あることが求められるなど、要件が厳しい