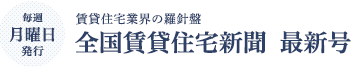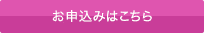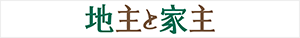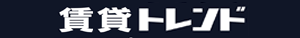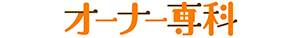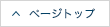設立9年、会員企業400社
一般社団法人シェアリングエコノミー協会(以下、シェアエコ協会:東京都千代田区)は、2032年には市場規模15兆円を超えると予測される成長マーケットの業界団体で、会員企業が約400社加盟する。協会設立の背景と活動目的を、上田祐司代表理事に聞いた。
CtoCサービス 規制緩和が目的
―シェアエコ協会とは、何を目的に発足した協会なのでしょうか。
対面で行う個人間のモノ・サービスの貸し借りを、自由化することです。シェアリングエコノミーは、インターネットを介してこれを実現するものです。例えば、ことの是非はさておきSNS上での情報交換・発信は自由に行えるのに対し、対面で誰かに有償で家や食事を提供しようとする、車で送迎しようとする、となった途端に法律の規制対象となります。やろうとしていることは、助け合いなのに。日本にはさまざまな法律・制度があり、それらが個人間の取引にも適用されることで、シェアリングエコノミーの発展が妨げられることを懸念していました。それに加えて、個人間のモノ・サービスの貸し借りにおける安心安全な利用環境を整備するためにも、官民の連携が必要だと考えていました。そこで国に対し、意見や要望を出していきたいと思っても、個人や一企業としての発言では国を動かせません。ある程度業界の総意として提言することを目的に、シェアリングエコノミー協会を発足しました。
―2016年に設立されました。
発起人は、私とスペースマーケット(東京都渋谷区)の重松大輔社長、アドレス(東京都千代田区)の社長で、当時はガイアックス(同)に在籍していた佐別当隆志社長の3人です。
国への提言効果 骨太方針、重要施策
―国に要望を出していくという目的の達成度は。
政府とは、シェアリングエコノミーやプラットフォームビジネスに関する幅広い政策議論に参画できるまで、関係性を築いてくることができました。その結果、「経済財政運営と改革の基本方針2024」(骨太方針2024)などの閣議決定文書において、シェアリングエコノミーの推進が重要施策として位置づけられたほか、個別の政策分野でも、24年4月には「自家用車活用事業(日本版ライドシェア)」の開始、同年11月に施行した「二地域居住促進法」の成立と、国への提言が成果につながりました。一方で、まだまだ乗り越えるべき課題は多いです。
―どんな課題でしょうか。
例えば、「ライドシェア」です。第2種運転免許を持たない一般のドライバーが自家用車を使い有償で送迎サービスを提供するというものですが、地域や時間帯に制約のない形での実現には至っていません。「ペット版民泊」など、業法の見直し議論に着手できていない分野もまだ残っています。
ライドシェア普及 国民の意思が重要
―シェアリングエコノミーを推進するために、国とコミュニケーションを取っていくことが大事な存在意義になっていると。一方で、〝シェア〞に含まれる領域が年々拡大しています。交渉すべきポイントもますます増えていくのではないでしょうか。
はい、先にも述べたようにまだまだ交渉はし切れていません。ただ国への働きかけで気が付いたのは、政治家はあくまでも国民の代表者であるということ。つまり、国民の考え方が変わることでシェアリングエコノミーは推進されていくのだと考えます。裏を返すと、シェアリングエコノミーの推進を規制しているのは、国民なのではないかということです。その例が、ライドシェアです。
―国民自らが、ライドシェアの普及を妨げている?
こんなにも普及が進まないのは、世界を見渡しても珍しいことだと思います。既存業界の抵抗が大きな要因ですが、新しいものに対してディフェンシブ(防御的)である国民性も理由の一つかもしれません。また日本の国民は「違法」という言葉に敏感だと思います。
―だから活発な議論も起こらない。
民泊の事例では、民泊新法の施行後で、5万〜6万件あったという民泊が3分の1にまで減ったというニュースがありました。結果的に、3分の2は違法だったということですが、国民のニーズから始まった民泊を法律により整理整頓するという議論の在り方はいいことでした。例えば10年以上前の法律にのっとったサービスに違和感を抱かず「違法だから考えることをやめる」という、国民のマインドセットを壊したいです。
自治体を巻き込む 人口減待ったなし
―課題として挙げた国民の意識変化。ユーザー向けに取り組んでいることは。
ユーザーに近い存在である、自治体を巻き込んでいくことに注力しています。具体的には、当協会が運営し、全国約190の自治体が参加するコミュニティー「シェアリングシティ推進協議会」の参加自治体を増やしていきたいです。ここでは、参加する自治体の取り組み事例のデータベース化や、地方におけるシェアリングエコノミーの活用実態を調査することで、国などへの提言資料に活用しています。特に人口が減少している地方の自治体にとっては、市民に対して公共のサービスを提供し続けることは現実的ではありません。モノ・サービスをシェアすることができれば、市民同士で助け合うことができます。このときに、法・制度が足かせとなるのであれば、自治体と協力して国に働きかけを行っていきます。
―24年11月に開催した「SHARE SUMMIT 2024(シェアサミット)」のテーマは「公民連携」でした。
テーマ設定が奏功したのか、2500人(オンラインを含む)の参加者のうち、自治体関係者は130人を占めました。自治体の参加と、自治体と組みたいサービス事業者の比率は例年に比べ劇的に高かったです。人口減少に対する取り組みや子育て支援など、各自治体が掲げる課題に対し、解決に導くシェアリングサービスとの出合いを提供する案内役の機能を、当協会は担っています。
―シェアエコ協会の今後の展開は。
当協会は、シェアが好きな集団を目指しています。シェアリングエコノミーを個人のライフスタイルとして推進することで、国民の意識を動かすことができると考えます。
(2025年1月27日9面に掲載)