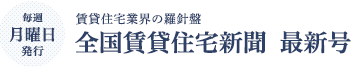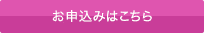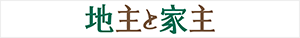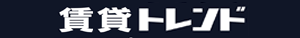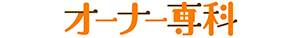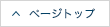カスタマーハラスメント(以下、カスハラ)への対処が賃貸業界でも課題となっている。カスハラに対する方針を公表した管理会社を取材し、具体的なカスハラに対する取り組みについて紹介する。
青・黄・赤色信号で判断
茨城県を中心に約2万3600戸を管理する香陵住販(茨城県水戸市)は、社内の部署を横断する部会をつくり、カスハラへの対応を進める。
同社の従業員数は正社員が229人で、臨時雇用は年平均81人。うち、賃貸管理部門の正社員は53人で、臨時雇用が19人。
カスハラ対策へ本格的に動き始めたのは、2023年4月ごろ。それまでも、20年の創立40周年を機にネームプレートを新調する話題が出たときに、ネームプレート自体を取りやめる判断をするなど、問題意識はあったという。さらに社内のコンプライアンス委員会で、カスハラに関する問題提起が度々あったことを受け、本格的に検討を開始した。
対応方針の検討にあたって、23年4月に社内でアンケート調査を実施。全従業員約230人に対して調査し、130人から回答を得た。カスハラ被害の経験が「ある」と回答したのは51.5%。特にPM(プロパティマネジメント)部門で「ある」との回答が多かった。上位に挙がったのは「大声で威圧された」が70.1%、「長時間の拘束」が61.2%、「不当な要求を受けた」が59.7%だった。
具体的な被害例としては「胸ぐらをつかまれて、暴力的な言葉を言われた」「雨漏りしている箇所を舐めろと言われた」など。被害のほとんどが入居者からだったという。
24年7月にカスハラに対する対応方針を公表。同年10月には、コンプライアンス委員会の下、カスハラ関連の検討を行う小部会を設けた。小部会の構成員は5人。賃貸管理の責任者も参加し、現場の意見を積極的に取り入れる。小部会において社内マニュアルの作成に取り組む。
足元ではマニュアルに載せるカスハラ判定の基準について、議論しているところだという。カスハラの判断基準は国や自治体が一定程度示しているが、個別具体的な判断については各業界、各事業者に委ねられている。
同社では、他社の取り組みを参考に、被害事例を青・黄・赤色の信号に分類することを想定。信号ごとの対応方法を明確化する方針だ。例えば、青の場合は「正当なクレーム」として対応、黄はカスハラに該当するか上長と検討、赤はカスハラ事案として関係機関と連携するなどだ。中野大輔取締役は「年齢や経験年数によって、カスハラに対する感覚が違う。色分けについてはまだまだ議論を重ねていく必要がある」と話す。
今後、電話の自動音声応答システムや、外部の近隣トラブル解決支援サービスの導入も視野に入れる。
会社のファンをつくる、という同社のスタンスを従来通り大事にしながらも、カスハラへの毅然(きぜん)とした対応をしていくべきだと同社は考える。
香陵住販
茨城県水戸市
中野大輔取締役(54)
(2025年6月2日2面に掲載)